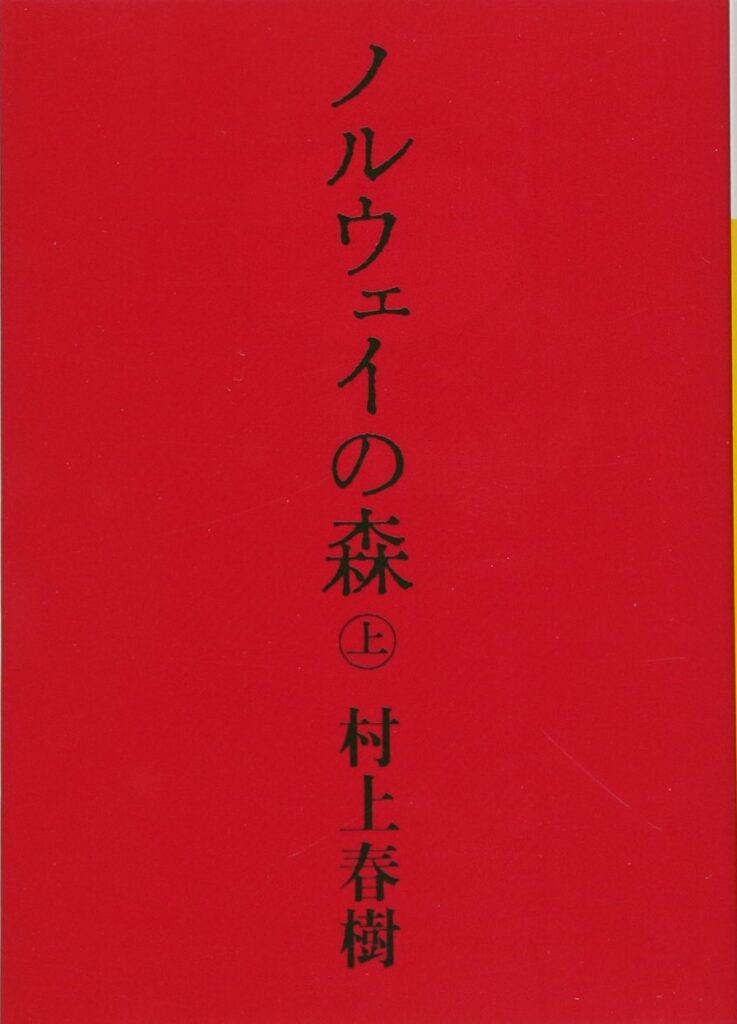凛として
― 心で味わう日本酒の想いと味 ―
路地裏にあるカウンター席だけの小さな飲み屋。その日その日の数限定の格安の刺身と特別品が評判で開店前から列ができる。客同士も密着する状態で、互いに隙間や会話を譲り合うような家族的な雰囲気の店でのことだ。
「寂しそうだから、一杯だけ注いであげるよ」
私が飲む『赤星』(サッポロラガービールの愛称)の大瓶を手に取ると、一つ席を置いて座る女の子が注いでくれた。それが屈託のない彼女との出会いだった。
携帯電話に入った知人からのドタキャンに不満をつぶやき、店の人に席が空くと告げた。そんなやり取りが聞こえたのか、あるいは猫背気味に飲む私が寂しそうに映ったのだろう。
「背を伸ばしてね、お兄さん」
彼女は宣言通り一杯だけ注ぐと、連れの同年配の女の子との話に夢中になった。
全国の蔵元を訪ねては酒を仕入れる店員と目が合った。一連の流れを見ていたような(残念でした)と含み笑いをして、「島根の酒が入っていますよ」と一升瓶を手にした。それが青砥酒造の『蒼斗七星』だった。
夏の日差しが残る夕方にほどよい爽やかな『蒼斗七星』を、数限定の刺身と文庫本を相手に二合ほど飲んだところで、入り口に並ぶ列に遠慮して席を立った。
電車の中で気が付いた。読みかけの文庫本を忘れてきたことに。戻るのも面倒で、それに待つ間の相手にと古本屋の百円均一で買った既読の本だった。ところが携帯電話に飲み屋から「預かっています」とご丁寧に連絡が入り、一週間後に受取りに行くと告げた。
「お兄さん、こっち、こっち」
店の開店を待つ列の中からかの女の子の声がした。あの日、私の忘れ物に気づいた彼女は追いかけた。彼女も読んだ村上春樹の『ノルウェーの森』の不安感が衝動的な行動に走らせたらしい。
「あの時、お兄さんの青春と私の青春が交じり合いあったのよ。それで追いかけてしまいました」
『ノルウェーの森』を読む還暦ほどの男の姿と、なぜ読むのか思い描けない男の心に、無性に寂しさを感じたという。それは彼女の淡い別れを思い起こす呼び水でもあった、
『赤星』で喉を潤すと二人は『蒼斗七星』を注文した。
「恋ってなんですか。私、愛より、恋がすきなんです」
『愛』は一途にさせる唯一無二、でも『恋』は夜空に輝く星のようだと話す。
「素敵な恋をしたんだね」と言う私に、「昼間には見えない恋なの」と長い睫毛を震わせた。
「私、キャバクラ嬢です。昼間は倉庫のようなところで働く事務屋さん」
デザイナーを目指して上京し、ところがテレビドラマの東京生活とブランドに振り回され、気が付くとカード地獄。
「あの日は、別れた彼の誕生日でした」
文庫本を手に追いかけた後に、真似て飲んだ『蒼斗七星』は重くて酸っぱかった。今日は爽やかな甘味がして、まろやかな酸味を感じますと首を傾げ、すごく幸せな感じですと微笑んだ。
日本酒は難しいお酒だよと言うと、余計なことまで話した。「飲む器でも、飲む相手でも、そして店の雰囲気でも、自分の心模様でも味が変わる。まるでわがままな女の子だな。それがまた楽しいけど・・・」
「天真爛漫な女の子でしょう」とそっと諭す。彼女には相手を傷つけることなく、楽しい話へとリードするコミュニケーション力があった。
「同じお酒、頼んでいいですか」。文庫本を持って走ったお礼に奢るといった。
「お肉と天ぷらと焼き魚、いいですか」。好きなだけ食べていいよとすすめた。
「お酒のラベルのデザイン、七夕の短冊のようですね」。確かに「七星」に引きずられる。
「瓶に願い事を指で書いたら叶うかもしれないな」
「見ないでください」と、人差し指で一升瓶をなぞっていた。
「何をお願いしたんだ」「また会えますようにとお願いしました」「そうか、素敵な彼だったんだな」。
「お願いがあります。今のように背筋を伸ばしてお酒を飲んでくれますか。私、そんな男の人が好きです」
その日から、ひとり酒は意識して背筋を伸ばす。歳を取ればとるほど意識して背を伸ばす。
あの夜、夢がかなったらここで飲もうと約束した。あれからたまに飲みに出かけたが、来たという噂も聞かず、偶然会うことなかった。やがて、客も変わり、店の店員も変わった。私の足もしだいに遠のいた。
駅のホームで彼女は、七色の夜光虫が輝く池袋の空を背に言った。「お話しできてよかったです。ご馳走になった『蒼斗七星』は、私の歩む人生の『北斗七星』に思えました。私、キャバクラを辞めます。そして、お話の島根県、いつか訪ねてみます」。そして文庫本を掴むと「思い出にください」と微笑んだ。

蒼斗七星
青砥酒造株式会社 (安来市)
PR
PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼