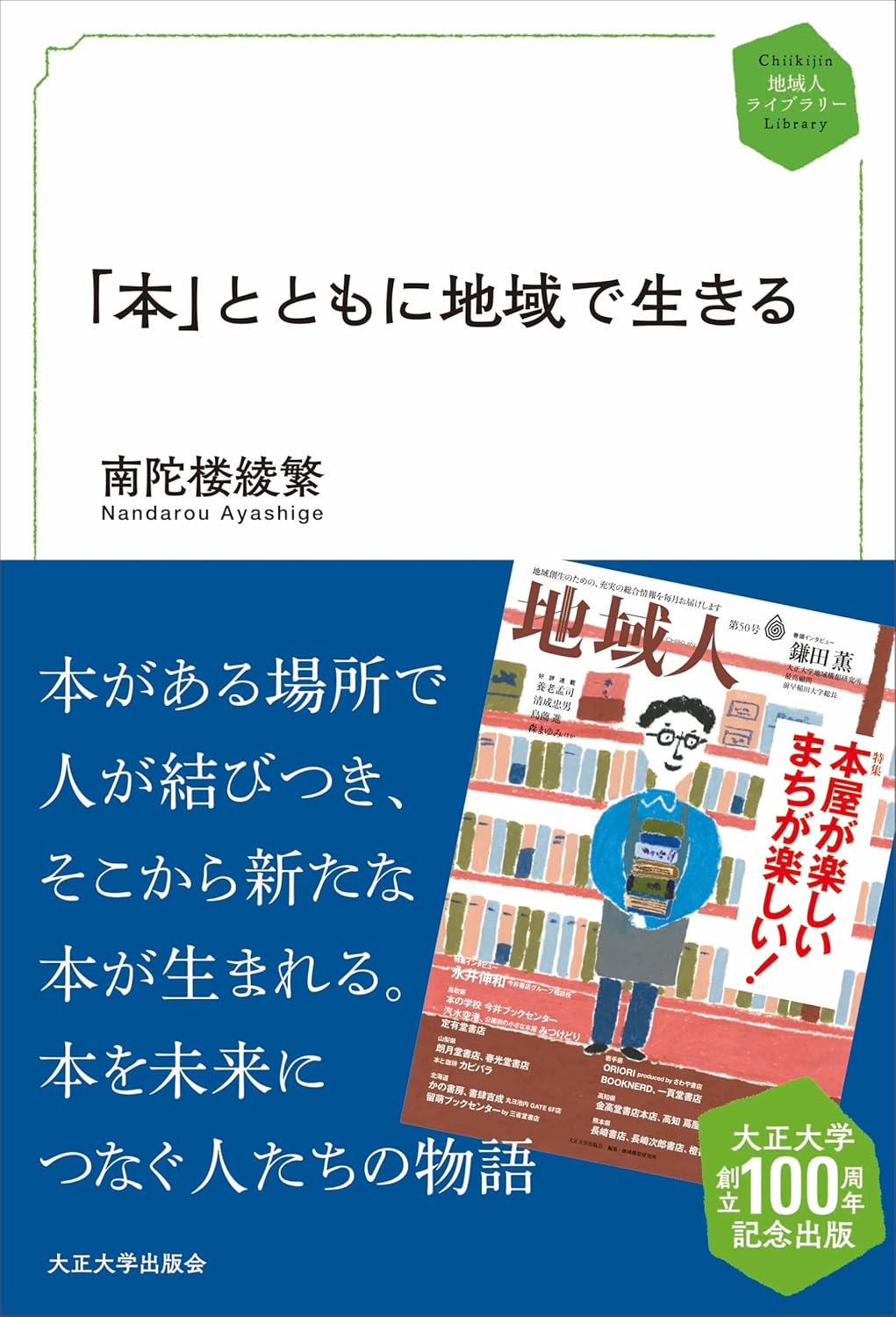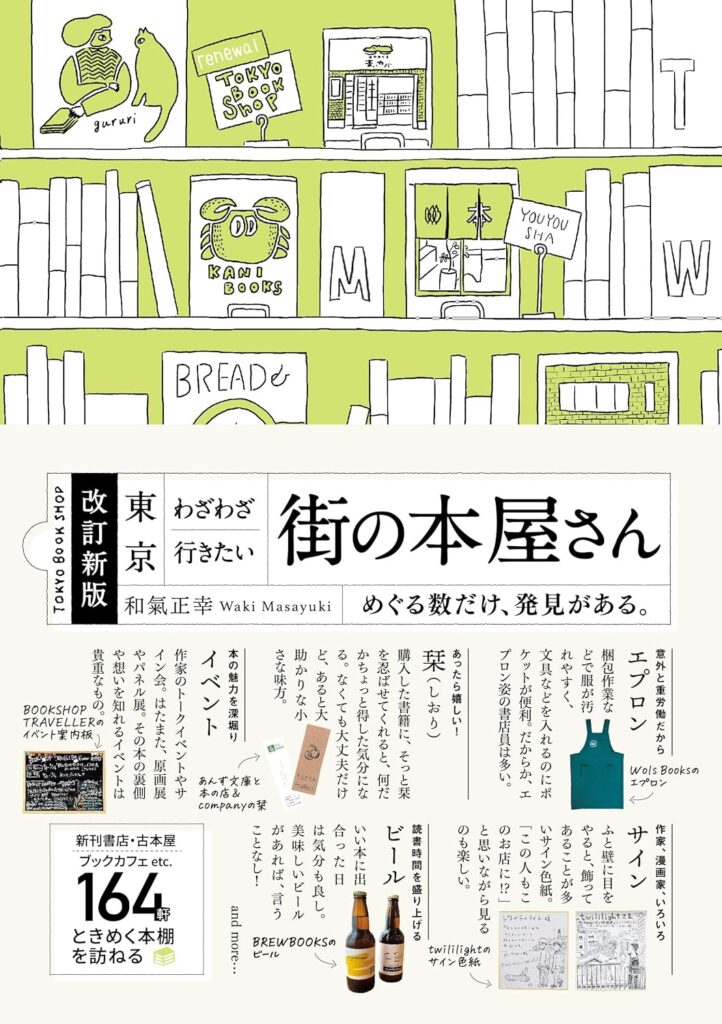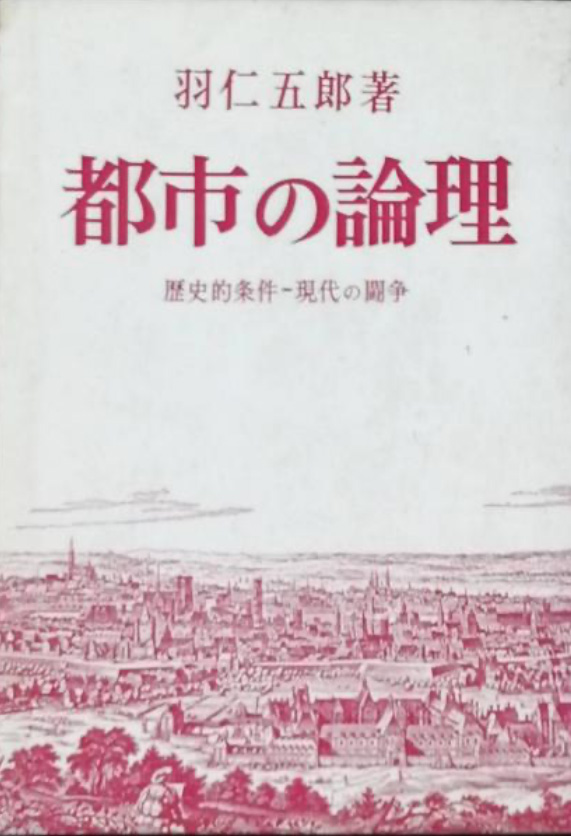『「本」とともに地域で生きる』旅先の寄り道、本屋・図書館
― 本という普遍性と関係という個別性 ―
書籍紹介
『「本」とともに地域で生きる』 著者・南陀楼綾繁、発行・大正大学出版会、発行日・2024年11月5日、定価・1800円(税別)、四六判、292ページ【購入する】
旅先の寄り道
旅に出ると必ず寄る所があります。古本屋と小さな書店。もしかするとここで過ごす時間が長いのかもしれません。探していた本や意外な本に出会うと鞄が重くなることも考えずに買い込むのです。
古本屋ではありがちな寡黙に座るオヤジさんやオカミさん。やがて本を挟んで話し込み、お茶までいただくことがあります。本屋さんの地域コーナーなどワクワクします。店主の嗜好というか思想が現れるからです。うろ覚えの地元にまつわる歴史や文化を語り、関係本を紹介して頂く。そこから広がる話の輪と出会いは、コミュニケーションの場所と言ってもよいでしょう。本屋や古本屋は「本を売る」ところだけでなく、出会いと驚きの空間です。

厳しい書籍業界
とはいえ現実は、本が売れなくなった、本を読まなくなった、そんな言葉を何十年前から耳にします。本が最も売れたのは、本に飢えた敗戦直後から80年代前半までではないでしょうか。
現在は、書店で見てネットで購入する、ブックオフで買い売る、ネットで検索して電子ブックで十分等々、買い手(消費者)のニーズやウオンツにあったサービス体系に変わりました。マーケテイング理論でいう4Pから4Cです。
書店のマージンは定価の22%、大量に売ることに努めてきました。出版社視点ならば取次店(東販日版)の7-8%がかかり(収めた書籍がすべて店頭に並ぶわけでもない)、手元に入るのは定価の約70%(比率は出版社のブランドや歴史で変わる)。著者の印税、デザイン・編集費に版下製作、そして紙代に印刷・製本、そこに人件費・固定費。重版を続けない限り出版社もやっていけません。
そうです、本屋は本を売って生計を立て、出版社は本を売って存在しています。買ってもらえなければやがて倒産・閉店するしかありません。そこで本を売るだけでなく他の付加価値提供を考えるのです。古くは著者のサイン会に文化講演会、大学の教科書(副読本)指定、数年前からは書店と珈琲店の併設や大型付録の雑誌に広告中心のファッション雑誌。私が編集者の頃、開店前の書店に行き、店の掃除をして店頭の目立つところに書籍を平積みにしてもらえないかと交渉しました。企画のネタにもなりました。

創意工夫の書籍業界
独特な努力と新たなサービスを試行錯誤するのは出版社だけではありません。書店も古本屋も図書館もいろんな施策を展開しています。
・本をよく知る本屋
書籍をよく知る本屋があります。池袋のJ店は、売れ筋やブームでなく時流をとらえた書籍選びと展示をします。結果、一冊買いに行ったのに渋沢栄一を二枚出しています。
・シェアブック(シェア型書店)
ここ数年、意外なところで出会うのがシェアブックです。その特徴からコミュニティ・書店と呼ぶ方もいます。
シェアブックとは、複数の棚や区画、ボックス(例えば50センチ四方)を置き、複数の棚主がそれぞれの企画で書籍を出品し、皆で書店を運営します。棚主は出店料と販売した本の手数料を費用として提出します。店長は棚主が交代で行い、なかにはコーヒーの販売もありコミュニケーションの場となっています。取次を通さないことで、作った本を店長として販売もできます。新刊もあれば古本もあり、なかには貸本もあります。現在、全国に90店あり(推定)、個性ある独特の展開をしています(無人店舗・会員制等)。今後急速に拡大するでしょう。コンピューターでいえば集中型から分散型で、これがインターネットで繋がると途方もない価値を創出する書店へと変身するのではないのでしょうか。
参考までに一点書籍を紹介します。これも西日暮里のシェアブックでお話しできたお礼に購入しました(その日の店主は本好きの建築設計士)。
和氣正幸著『東京わざわざ行きたい街の本屋さん―めぐる数だけ、発見がある―』。店内のカラー写真もふんだんで、見るだけで特徴や主張がうかがえます。
・図書館の検索
年間読む本の大半が図書館の本になった昨今です。図書館の書籍のデータベースが充実し、書籍名や著者名だけでなく、目次や紹介文などからもキーワード検索でき、意外な書籍に辿り着きます。返却の手間を気にしなければ無料の図書館が最高です。図書館運営の工夫として、検索をどのように活かすかだと思います。
「本」とともに地域で生きる(書籍紹介)
やっと書籍の紹介です。さらに、正直に申せば、この本は図書館で借りました。
新刊コーナーの書籍を借りるかどうかは、まず目次と奥付に目を通し、序文やあとがきを読んで決めます。
本の魅力は本文の中身を抽象化した目次の出来栄えです。『検索』を売りとするwebとの大きな違いであり、面白味です。今回は目次と奥付で借りました。
・目次
「本書は、大正大学出版会が発行する雑誌『地域人』で書いた、本屋、図書館、ローカルメディアという、『本』についての文章をまとめたものだ」(はじめに)
本書は、全国を歩いて見つけた書店・図書館・ローカルメディアを取上げています。全体は三章から成り立ち、それぞれの店舗・図書館・ローカルメディアのコンセプトや物語、そして出会いを本と地域の関りを通して紹介します。
第一章 本屋 自分自身に帰る場所
インタビュー⓵ 永井伸和(今井書店グループ相談役) 山陰から「本の世界」を見つめて
インタビュー➁ 辻山良雄(「本屋Title」店主) 書店の本屋は本を売る場所からコミュニケーションの場に
書店紹介 34店舗。島根無、鳥取3店舗
第二章 図書館 郷土の「知」を未来に手渡す
島まるごと図書館構想(島根県海士町)など6館
第三章 ローカルメディア 小さくても届く言葉
『あめちのことづて』(熊本県水俣市)など48誌
・島根については2誌、鳥取無
・著者紹介
奥付の著者紹介から南陀楼綾繁(ナンダロウアヤシゲ)氏の略歴を一部抜粋します。
「1967年、島根県出雲市生まれ。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の前代表。全国各地で開催される「一箱古本市」の生みの親でもあり、各地で開催される多くのブックイベントにも関わる」
「読者が『本と遊ぶ』場所」としていろいろな活動を企画するアイディアマンであり行動派です。
・本のある場所
カンの良い人ならば、なぜ『島根国』で取上げたかお分かりでしょう。理由は「島根」との関りです。
出雲市生まれの南陀楼綾繁氏だけが、島根県の関係者ではありません。
第一章の「本屋 自分自身に帰る場所」の「インタビュー①山陰から『本の世界』を見つめて」の永井伸和氏は、鳥取・島根で書店展開と出版や文化活動を行う今井書店グループの相談役です。第二章の「図書館 郷土の『知』を未来に手渡す」では、島根県海士町の「島まるごと図書館構想」が紹介されています。第三章の「ローカルメディア 小さくても届く言葉」では、「BOOK在月」(島根県松江市)、「みんなでつくる中国山地」(島根県邑南町)がとりあげられています。
図書館とローカルメディアについては、是非、書籍を購入して島根旅の参考としてください。また全国の本屋、図書館、ローカルメディアも旅の羅針盤にご活用ください。
ここでは地域に根差した今井書店について紹介し、地域と共に「本と遊ぶ」を粘り強く展開しておられる著者や各店主の熱い思いと夢へのエールとさせていただきます。

書店を中心に町は創られる
・人生の岐路に今井書店(松江・殿町)があった
高校時代を松江で過ごした私には、今はない松江・殿町の今井書店は数少ないデートの場所でした。1960年代後半の今井書店は混んでいました。勤勉な彼女は二階の受験・参考書コーナー、私は一階の書籍コーナー、とくに岩波文庫の書棚の前で「★」ひとつの文庫本を探します。「★」ひとつは50円、喫茶店のコーヒーが80円、ショーピーが50円の頃です。彼女が旺文社の『蛍雪時代』を買う日、私は『朝日ジャーナル』か『月刊ガロ』を奮発しました(今井書店で『平凡パンチ』は買えなかった)。
今井書店は東京や文化・思想を繋ぐ窓口で、刺激を受けた私は無限の世界を夢見ていたのです。書店を出ると松江城の城山への道、「大学どうするの」が彼女の口癖でした。
そんな総合書店の今井書店が姿を消したのが、昨年(2023)のことです。2020年リニューアルした今井書店は地元関係の書籍や地元出身者の書籍を販売し、帰郷の折は必ず寄り購入しました。建物の二階に「おせわさん」があり、この団体も今井書店には随分お世話になったと聞いています。詳細は、当サイト『地方創生の活動』の『おもてなしの心から街づくりへ』を参照ください(※)。
・今井書店が果たしたこと
今井書店や永井伸和氏が果たされた役割と業績についても、直接取材しておりませんので紹介の書籍をご確認ください。ただ高校時代の三年間、そして近十年、殿町の今井書店に接して、今でも言えることは永井氏の次の言葉です。
「地域と本の未来をどう考えていますか」の問いに、永井氏は応えます。「地域の多様性や違いを生かして、質的な進歩を、求めてほしいです」(2019年10月掲載)。
今井書店は地域の特殊性を活かし、地域や町づくりに多大な役割を担ってきました。それこそが地域に密着し、かつ世界へと視野を広げるファシリテーターでもあったのです。
惜しまれるのは、殿町から今井書店が消えたという事実です。努力を怠って消えるならば社会の摂理です。しかし、努力を重ね、さらには地域に密着した書店展開を続けられての判断でした。
旅のついでに、本屋に、図書館に、そしてここではとりあげていない古本屋に是非足を運んで、その店の雰囲気を、考えを、そして思いを感じ取って頂きたい。さらにはローカルメディアから地方の息吹を感じていただきたいものです。

おしまい 町づくりにかかせない本屋と市場
高校二年生の時です。とある教師に「東京の高校生は、このくらいの本は読んでいる」と鼓舞されて、殿町の今井書店に一大ベストセラーの羽仁五郎著『都市の論理』を予約しました。待ちました、ひと月も、ふた月も、待ち続けました。寮は緊急電話の取次ぎ以外はできず、学校帰りに日課のように訪ねたのです。ひと月も過ぎれば店員の顔色で分かります、来ていないことが。
やっと手にした、白地に小豆色の一色で書名と著者名、下段に中世ヨーロッパの建物の絵画の本。これで青山、九段、新宿の高校生と同じ位置に並んだと、笑む女性店員に頷きました。
その夜、理解できない自分の頭を恨みました。もっと勉強すればよかったと後悔しました。八つ当たりというのでしょうか、本を売るだけでなく読書会ぐらい開催しろよと、書店を恨んだかもしれません。でも本屋があったから手にすることが出来、雑誌の書評を立ち読みすることも出来、読み続けたのです。あのとき、書店は私のような若者の先生であり、先輩でもあり、そして社会への窓でもあったのです。
書店は大切です。もちろん古本屋も図書館も。そこには本や人だけでない色々な出会いがあります。「理解」「疑問」「後悔」「喜び」、さらには「未来」「見えないライバル」「考える努力」。そんな書店独特の出会いがあります。今はそれを「検索」で簡単に解決できるようになりました。その代わり自ら切り開く「苦しみ」や「喜び」はなくなりました。
もしかすると本屋には、出会いを求めて出掛け、疑問や限界、そして気づきを発見する喜びがあったのではないのでしょうか。
旅先の本屋や古本屋に図書館では、市場(いちば)と同じでその地の文化や風土、人間模様に出会えるのです。
町づくりには多くの人が集まる市場とともに書店が必要だと、あらためて教えてくれた本との出会いの思い出です。それが『町の論理』かも。
最後に松江駅前に喫茶店付きのシェアブックができたなら、と願う次第です。
PR
PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼