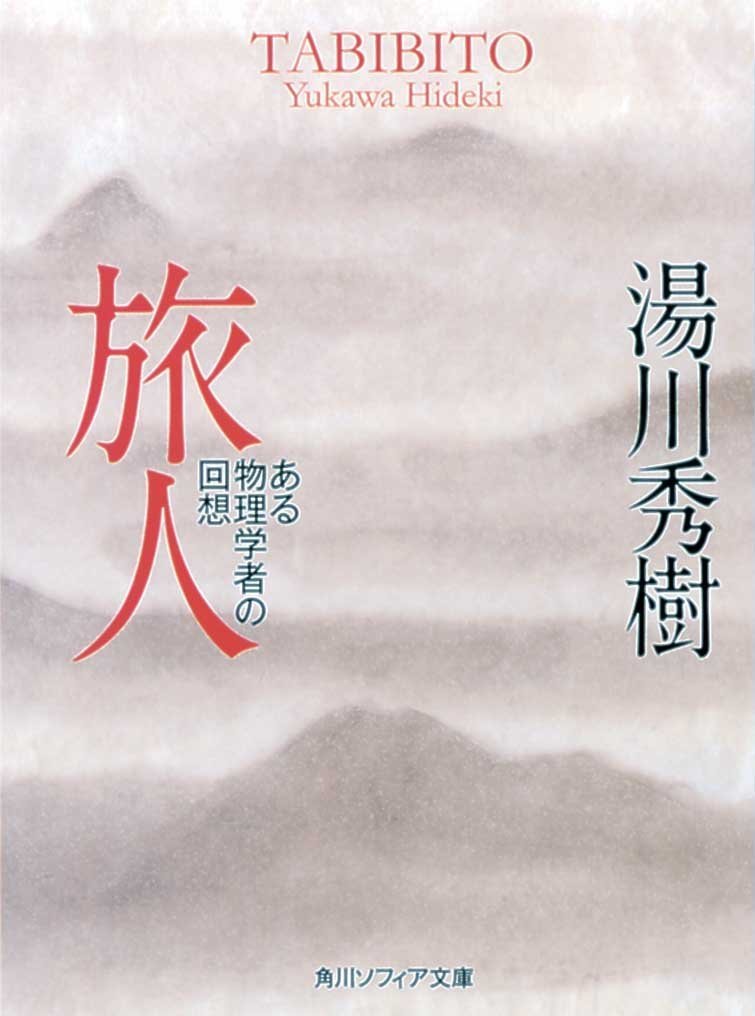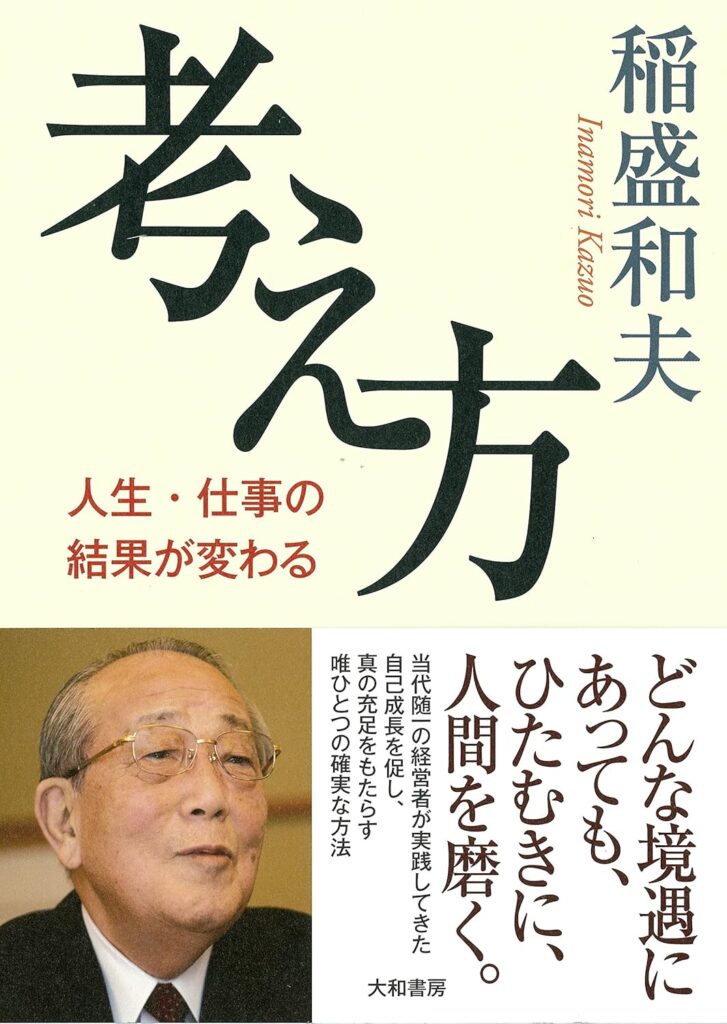7 濡れ縁で我流の禅を組む旅・萬福寺と医光院(益田) -随分遠回りをしたものだ、自分への旅-
- HOME
- 自然と観光
- 五感で感じる、島根の旅
- 7 濡れ縁で我流の禅を組む旅・萬福寺と医光院(益田) -随分遠回りをしたものだ、自分への旅-
7 濡れ縁で我流の禅を組む旅・萬福寺と医光院(益田)
-随分遠回りをしたものだ、自分への旅-
今回はこんな旅をしよう
中間子理論で日本最初のノーベル賞を受賞(1949)した物理学者の湯川秀樹(1907-1981)。その湯川秀樹の著書に、自身が綴った幼少期から27歳までの人生『旅人―湯川秀樹自伝―』がある。
人生は旅のようなものである。「一日生きることは、一歩進むことである」「ただ流行を追っていることは、つまらない生き方です」(湯川秀樹)。
「未知の世界を探求する人びとは、地図を持たない旅行者である」(湯川秀樹)。逆も真ならば「地図を持たない旅人は、未知の世界を探求する人びとである」
さて、今回は「未知の世界を探求する」旅人になろう。
あそこに行き、あれを見て、それを食べて、写真を撮って楽しむ、その為に事前にガイドブックを事細かく読みつくす旅ではなく、また何かにとらわれるのでなく、ひとりになって深くゆっくり深呼吸する旅の楽しみ方だ。
ゆっくり深呼吸する旅
自然しかない山の頂でも、清流の音に包まれる渓谷でも、あるいは心頭滅却した雑踏のなかでも、高いビルの上でも、軽く目を閉じて深くゆっくり深呼吸を繰返してみよう。そして自分の好きな音だけを、例えば風の音、光の音、薫りの音、鼓動の音、それだけを聞き分けて魅入って行こう。無理ならば、セミの鳴き声でも、クーラーの音でも、あるいはどこかから流れてくる好きな音楽でもよい。ただひとつの音だけを追い、集中しよう。やがて貴方は気づくだろう。音がまったくなくなったことに。もしかすると寝入っているかもしれない。それでもよい。心穏やかになるならば。
何処でもよいと言ったが、島根旅・萩津和野旅のついでに、雪舟の造った萬福寺と医光院(益田) の濡れ縁でやってほしい。言葉では残さなかった雪舟の心に気づくきっかけとして。雪舟が創造し、具現化し庭園を心に描き、地図にもない経験をしてみよう。


自分をときはなつ旅
『禅の思想』の筆者・鈴木大拙にこんな言葉がある。「もし真実をみたいというのであれば、それは真実ではない」。真実は固定されたものではなく、常に変化し続けるものである。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」。鴨長明『方丈記』より。
この世に変わらぬものはない、たとえ真実でも例外ではない。貴方の見ている景色も変わるなら、隣の貴方という他人が見ている景色も違うはず。それはあなた自身が変化して、常に同じ気持ちではないからだ。
濡れ縁から見る庭も同じで、今の庭と数分前の庭とは異なる。なぜならば、今の貴方と数分前の貴方とは異なるからだ。
何かにこだわり追い求め、許せないと思い続け、心のずれにくよくよすることが、いかに無駄なことかに気づくはず。目を開ければ同じ風景があるかもしれない。しかし、目を開けた貴方の心は変わっている。変わった心で見れば気づくはずである、既にあの庭ではないことに。そして座る濡れ縁さえも、変わった貴方の心模様を写していることに。

益田市萬福寺と医光院
益田市萬福寺と医光院については、当『島根国』サイトの『五感で感じる、島根の旅【シリーズ】水と光と風と肌』をご覧ください。
なお、ここでの萬福寺と医光院の説明文は、益田市観光協会webサイトより引用。
・萬福寺(まんぷくじ)
「時宗益田道場として平安時代に建立され、当初は安福寺と号し益田川河口付近にありました。しかし大津波で流出していまい、後の1319年、游行4代呑海上人が再興しました。1374年には益田七尾城11代城主が現在の地に移築して萬福寺と改称、益田家の菩提寺と定められました。
その後、1479年に15代城主益田兼堯が歌聖・雪舟を招き、石庭を造らせました。1866年長州征伐益田口戦争の際には、幕府軍の陣営となり総門は焼失しましたが、本堂や庫裏はそのまま残っています。鎌倉時代の建築様式の本堂(重要文化財)、雪舟が築いた庭園(史跡及び名勝)、仏教の教えを表す「二河白道図」(重要文化財)、南蛮貿易によりもたらされた「華南三彩壺」など、中世益田文化を代表する文化財が集まる寺院です。国重要文化財、国指定名跡及び名勝。」

・医光寺(いこうじ) (崇観寺・すうかんじ)
「臨済宗東福寺派のお寺ですが、もとは天台宗崇観寺の塔頭でした。崇観寺は1363年に創建され、足利将軍の台翰(手紙)をもって住職を任命したほどの格式のある大伽藍でした。益田兼見は本尊の釈迦如来坐像作成の大檀那(スポンサー)となっています。
文明年間(1469〜1486)第七代住職雪舟はこの崇観寺の塔頭のひとつに庭園を残しました。その後、崇観寺は 衰退していき、17代益田宗兼によって医光寺が開基しました。
医光寺の雪舟庭園は国史蹟および名勝に指定されており、 池泉鑑賞半回遊式の庭園で、鶴池に亀島を配置した吉祥の庭となっています。
毎年3月半ばには枝垂れ桜が華やぎを添え、5月には一面のツツジ、夏は緑が涼しく、秋には大きな楓が赤く染まっています。国指定史跡及び名勝、国登録文化財、県指定有形文化財。」

・濡れ縁で我流の座禅で瞑想
濡れ縁を、暫し旅人や見学者の邪魔にならないように右から左、左から右へとゆっくり歩いてみて、あぁーここがいいな、と感じたところに腰かけ、我流の結跏趺坐を組み、背筋を伸ばし半眼でゆっくり腹式呼吸を繰返す。気が散るなら目を閉じよう。やがて時という流れが消え、意識のなかからも消去される。日々の生活は楽しいものだ、と感じたら至福の世界に到達したと喜ぼう。
瞑想は無理することはない。楽しいことを考えよう。好きなタレントとのデートでも、百メートルのオリンピック選手となって金メダルを取る姿でも、はたまた政治家でも。その続きにどうなるか、目を開けたとき貴方が何を思うか楽しみだ。
プラス思考で禅を組もう
無茶苦茶に勉強をする、芸術性を、技術を磨く、また仕事をする。しかし、限界や運がある。なによりも、すべては無限ではない。むしろ日本的風土は未完で残す。
仏教に「老病死生」の教えがある。人には避けられない四つの苦しみ。自分のことでだけではない。親が子に思う「老病死生」、子が親に思う「老病死生」、好きな人や尊敬する人に思う「老病死生」。日々の関りによっては沢山の「老病死生」を抱えているだろう。
拝みなさいとか、お願いしなさいというのではない。また無欲や虚無の境地に立ちなさいとか、悟りなさいというのでもない。そんなこと言えた身分でも、人格者でもない。
ただ辛くなったら禅を組もう。真実など求めることもなく。ただプラス思考で。なにも解決はしてくれないが、明日も明るく生きていこうと思えば幸せだ。そして家族に、友人に、そして社会や自然に感謝できればもっと最高だ。
貴方の心構えひとつが「老病死生」に影響することもある。それが生きる目的や周りの慈悲の心かもしれない。
元京セラの社長でありJALの社長でもあった稲盛和夫の著書『考え方』のなかに、「プラス思考」という項目がある。プラス思考の一部を引用すると「利己的ではなく、『足る』を知り、感謝の心を持っている。善意に満ち、思いやりがあって優しい」。
プラス思考とは自己中心ではない。社会のために、人のために何をするか、その為には自分はどうであるかの考え方だ。是非、立ち読みでもしてほしい。旅(人生)は楽しいことの発見だ。そして探求でもある。
湯川秀樹にも、鈴木大拙にも、稲盛和夫にも、到底なれない無名の旅人の独り言。
PR
PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼